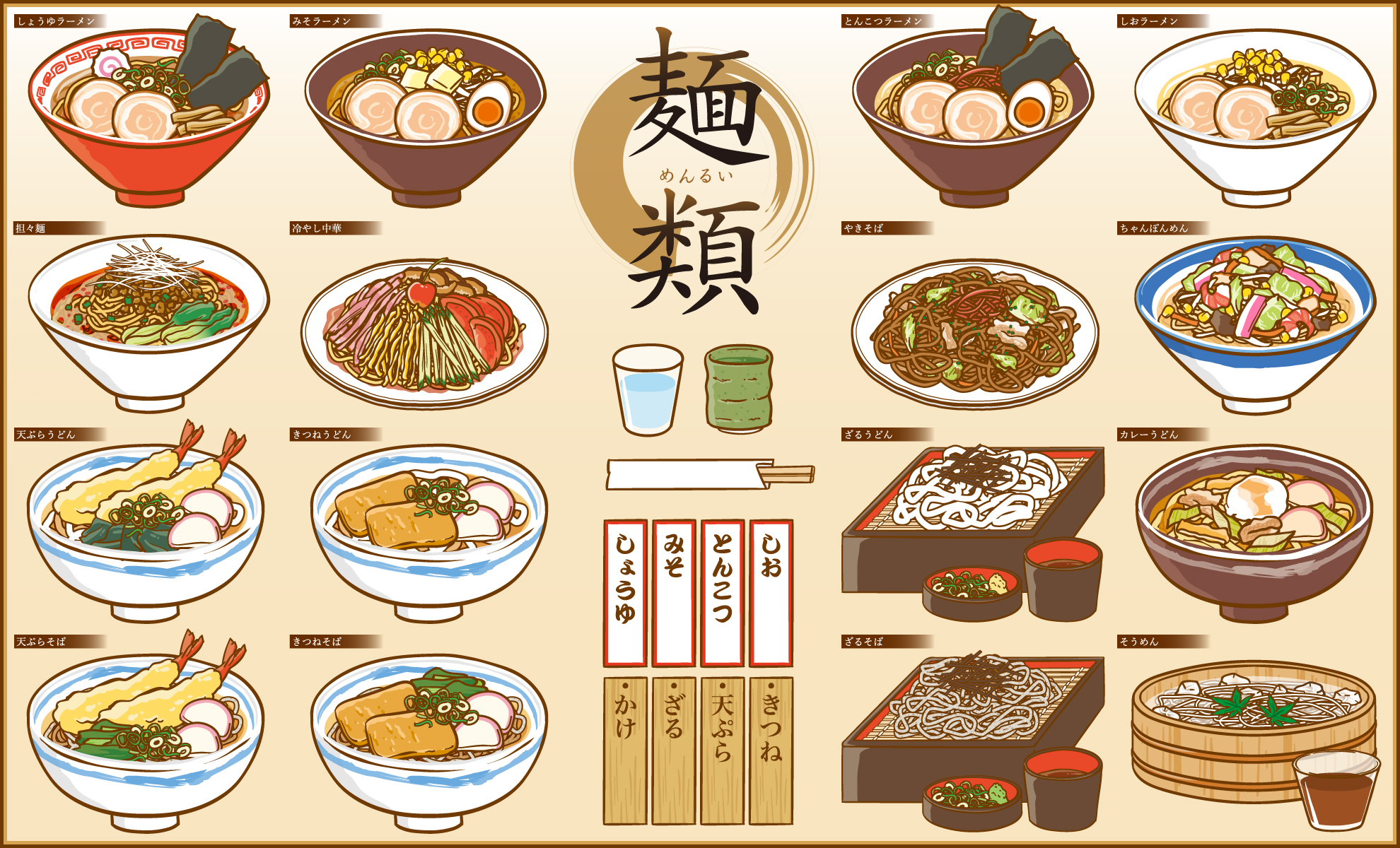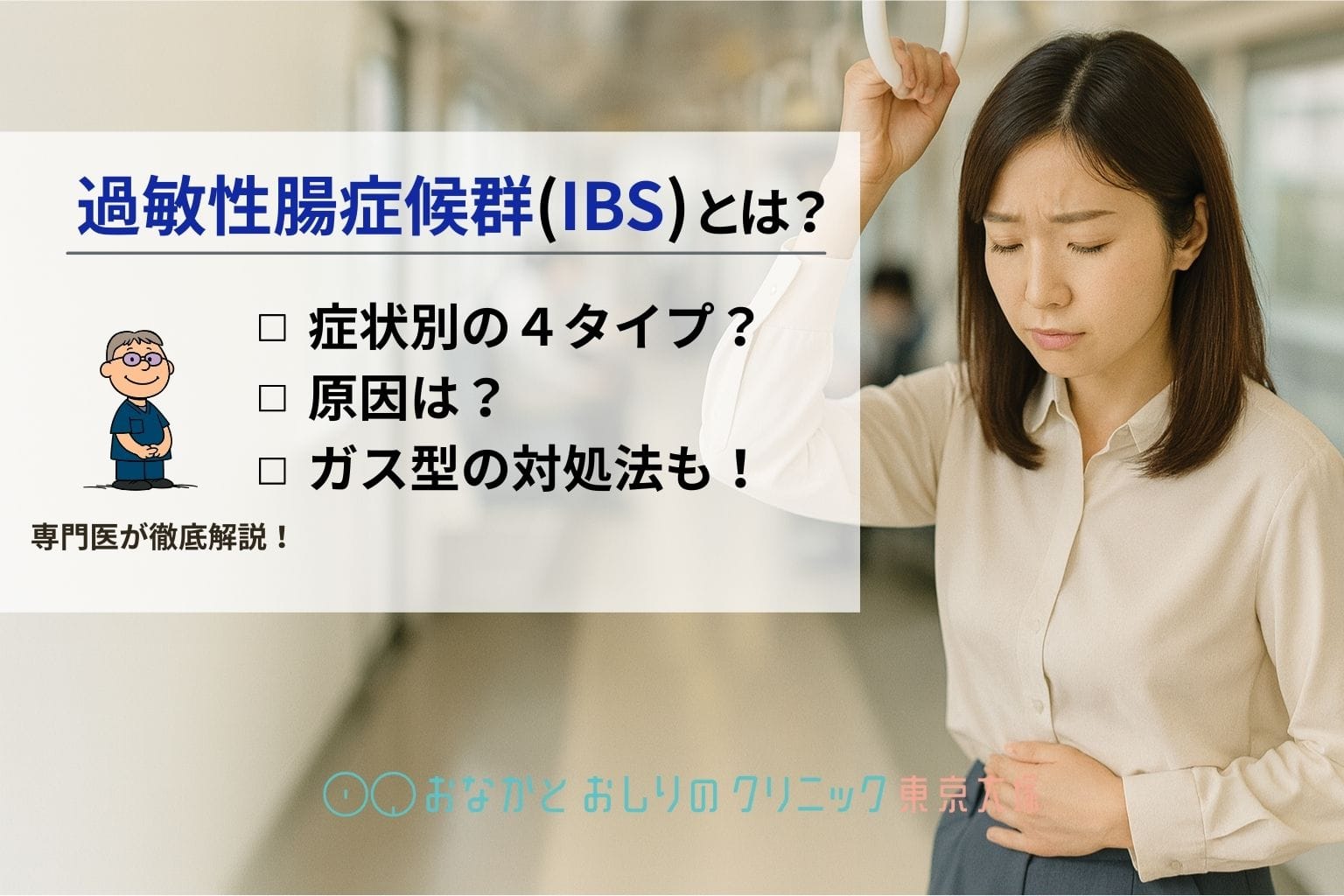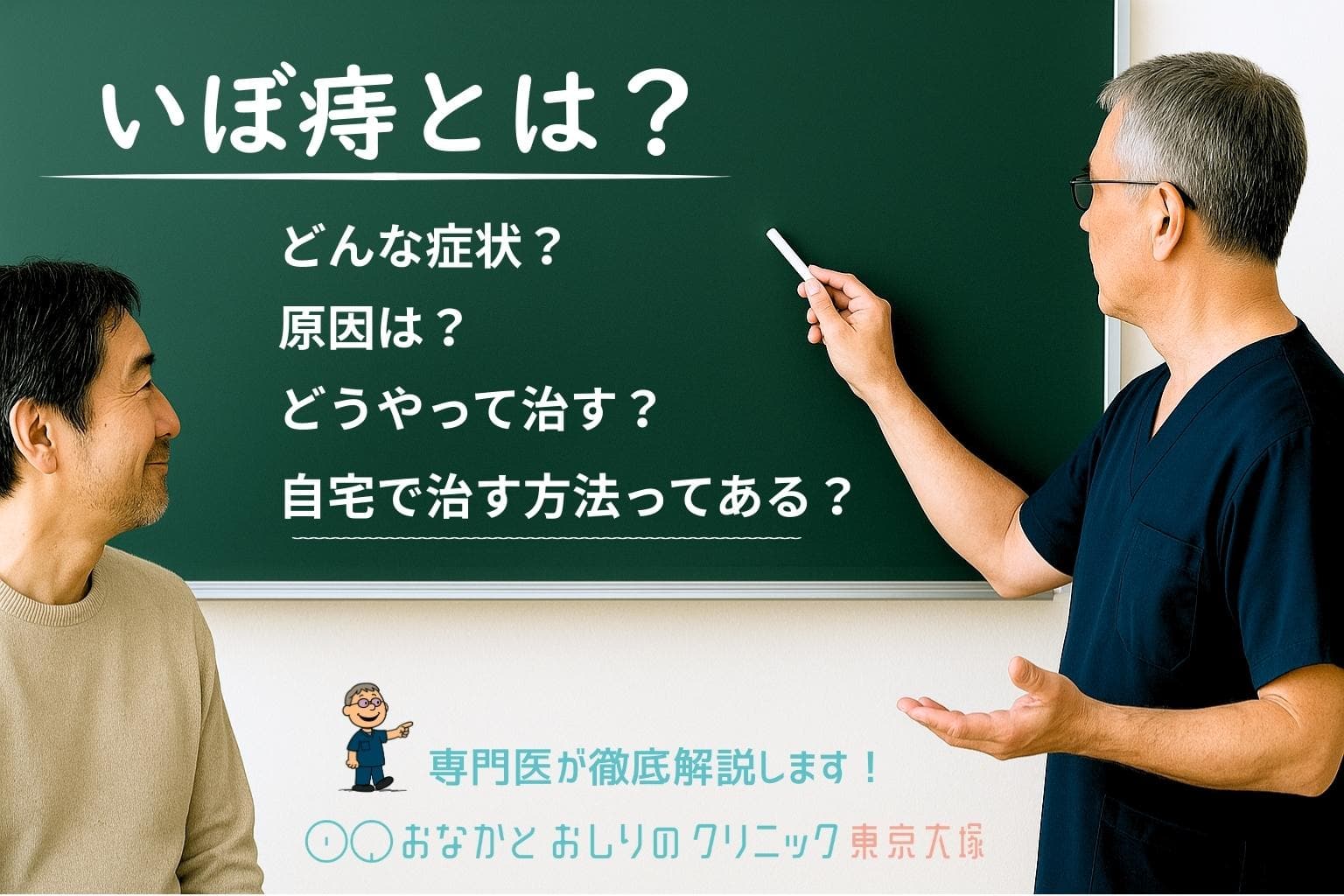2025年10月22日

朝晩は冷えるのに日中は暑く、気温が乱高下する――。
そんな季節の変わり目になると、「なんとなくだるい」「体が重い」「胃腸の調子が悪い」などの体調不良を感じる方が増えます。
実はこの不調、単なる疲れではなく、寒暖差によって自律神経のバランスが乱れることが原因のひとつと考えられています。
最近の研究では、気温の変動が大きい日ほど心拍変動(HRV)が低下し、
体の“自動調整スイッチ”である自律神経に大きな負担がかかることが確認されています。
また、自律神経の乱れは腸の働きにも直結します。
寒暖差で疲れやすくなったり、便秘や下痢が続いたりする場合は、
胃腸の不調の裏に他の疾患が隠れていないか、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)でチェックしておくと安心です。
寒暖差疲労とは?
「寒暖差疲労」とは、朝晩や屋内外などの温度差によって、
体温を一定に保とうとする自律神経に負担がかかり、疲労やだるさ、頭痛などが生じる状態を指します。
気温の変化に体がうまく対応できなくなることで、さまざまな不調が現れやすくなります。
気温差による自律神経の“混乱”
人の体は、外気温が下がると血管を収縮させて熱を逃がさないようにし、
反対に暑いときは血管を広げて汗を出し、体温を一定に保つ仕組みを持っています。
この調整を担うのが自律神経です。
ただし、朝晩と昼の気温差が6〜7℃以上になるような日は、
体温調整のスイッチが何度も切り替わるため、自律神経に大きな負担がかかります。
実際の研究でも、1日の気温変動(=日較差)がこの程度大きい日ほど、
心拍変動(HRV)が低下し、自律神経の働きが乱れる傾向が確認されています。
つまり「7℃」というのは厳密な基準ではなく、
“自律神経が乱れやすくなる目安”として臨床的にもよく使われている数字です。
個人差はありますが、寒暖差が5℃前後でも体調を崩す方も少なくありません。
自律神経が乱れると起こる体調不良
自律神経は、体のあらゆる働きをコントロールしています。
寒暖差でこのバランスが崩れると、体のさまざまな場所に不調が現れます。
代表的な症状
・全身のだるさ・疲労感
・頭痛・めまい・肩こり
・眠りが浅い、寝ても疲れが取れない
・胃もたれ・食欲不振・便秘や下痢
・イライラ・集中力の低下
特に、女性や高齢者、冷え性の方は体温調節機能が弱いため、寒暖差の影響を受けやすい傾向があります。
科学的にわかった「寒暖差疲労」のメカニズム
寒暖差によって体が疲れる――。
この現象は感覚的なものではなく、医学的なデータでも裏づけられています。
最近の研究では、気温の変動が大きい日ほど「心拍変動(HRV)」という自律神経のバランス指標が低下することがわかっています。
海外の研究:気温差が大きいほどHRVが低下
78人を対象にした研究では、気温の変動幅(寒暖差)が大きい日ほどHRVが下がり、
特に副交感神経の働き(リラックス側)が低下していました。
これは、気温差が交感神経を優位にし、体を緊張状態に導くことを意味します。
女性ではこの変化がさらに強く、寒暖差に敏感な傾向が示されました。
参考文献:Minna Tang, et al. The acute effects of temperature variability on heart rate variability: A repeated-measure study. Environmental Research. Volume 194, March 2021, 110655March 2021, 110655
高温環境実験:30分で自律神経が変化
別の実験では、WBGT 35℃の高温環境に30分滞在すると、
心拍数・体温・発汗が上昇し、副交感神経の働きが明らかに低下しました。
つまり「暑さや寒さの急な変化」は、たった数十分でも自律神経に負担をかけ、
その結果として“寒暖差疲労”が起きることが生理学的に裏づけられています。
参考文献:Shinji Yamamoto, et al. Evaluation of the Effect of Heat Exposure on the Autonomic Nervous System by Heart Rate Variability and Urinary Catecholamines. Journal of Occupational Health. 49巻(2007)3号.p199-204.
寒暖差疲労を防ぐ3つの習慣
寒暖差をゼロにすることはできませんが、日常の工夫で体への負担を減らすことは可能です。
自律神経を整えるための3つのポイントを紹介します。
① 服装で温度差をコントロール
重ね着や羽織ものを活用し、屋外と屋内の急な温度変化に対応しましょう。
首・手首・足首を温めることで、体温調整がスムーズになります。
② 湯船に浸かって副交感神経を整える
38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ゆっくり浸かることで、
交感神経の緊張が和らぎ、血流が改善します。
忙しい日でも“入浴タイム=体のリセット時間”として大切にしましょう。
③ 朝の光と睡眠リズムで自律神経を回復
朝起きたら太陽の光を浴びることで、体内時計と自律神経のリズムが整います。
夜はスマホを控えめにして、毎日同じ時間に眠る習慣をつけましょう。
体調不良が続くときは医療機関へ
「寒暖差のせいかな」と思っても、実際には別の病気が隠れている場合があります。
早めの受診が安心です。
放置せずチェックしておきたい理由
だるさ・疲れ・便秘・下痢などが長引く場合、
甲状腺の異常、貧血、胃腸疾患、自律神経失調症などが背景にあることがあります。
とくに胃腸症状が続く場合は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で腸の状態を確認しておくと安心です。
当院ではAI内視鏡による検査で、精密かつ短時間で負担の少ない検査が可能です。
当院のご案内
「おなかとおしりのクリニック 東京大塚」では、寒暖差による不調・だるさ・胃腸症状など、
自律神経の乱れを背景とした体調不良にも丁寧に対応しています。
高画質AI導入内視鏡システムによる大腸内視鏡検査のほか、
便秘・下痢・過敏性腸症候群(IBS)などの症状にも、根本原因を見極めた治療を行っています。

FAQ(よくある質問)
Q1. 寒暖差疲労は病気ですか?
A. 正式な病名ではありませんが、気温差による自律神経の乱れによって起きる生理的な反応です。
Q2. 寒暖差アレルギーとは違うのですか?
A. 寒暖差アレルギーは鼻粘膜の血管が反応して起きる「血管運動性鼻炎」で、
寒暖差疲労は全身の自律神経バランスの乱れによるものです。
Q3. どんな人がなりやすいですか?
A. 睡眠不足、ストレス、冷え性、運動不足の方は自律神経が乱れやすく、
寒暖差疲労を感じやすい傾向があります。
まとめ
寒暖差は自律神経に大きな負担をかけ、だるさ・疲労・体調不良を引き起こす。
HRV(心拍変動)を用いた研究で、その生理学的メカニズムが科学的に示されている。
睡眠・入浴・服装の工夫で予防し、症状が続く場合は医療機関へ。
胃腸の不調が続く場合は、大腸内視鏡検査で腸の健康状態を確認するのがおすすめです。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚
院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)
資格:日本消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
帝京大学医学部外科学講座非常勤講師
元帝京大学医学部外科学講座准教授
医学博士
院長プロフィール