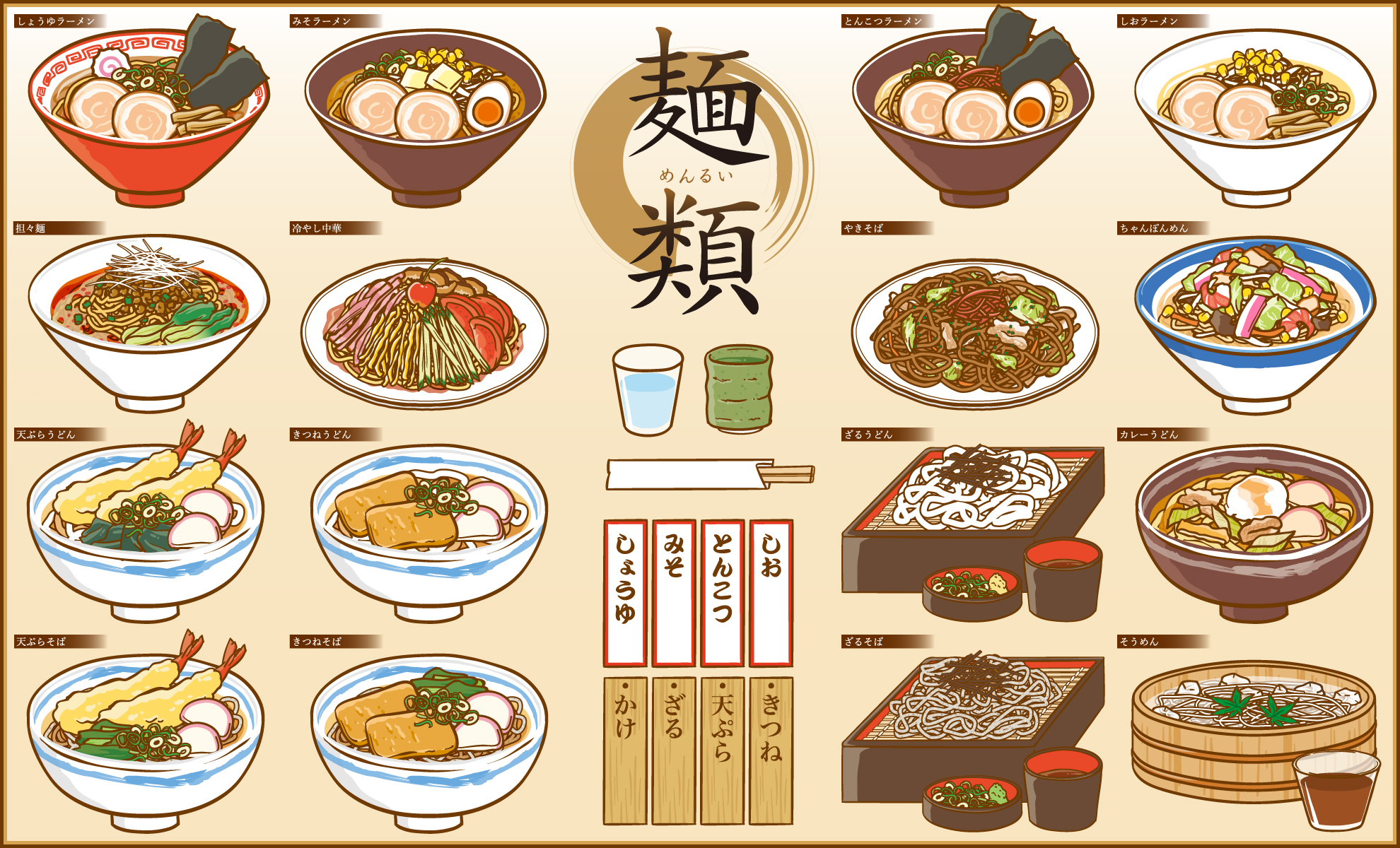2025年7月12日

秋は「食欲の秋」と呼ばれる季節。旬の食材を楽しむ機会が増える一方で、実は食中毒のリスクも油断できません。気温が下がり始めて「食中毒は夏のもの」と思われがちですが、秋には秋ならではのリスクがあります。
今回は「秋に特に注意したい食中毒」をランキング形式で紹介し、消化器内科専門医が原因や予防法も解説します。
日本における月別食中毒の発生状況です。1年の中で、秋は食中毒の少ない傾向にあります。
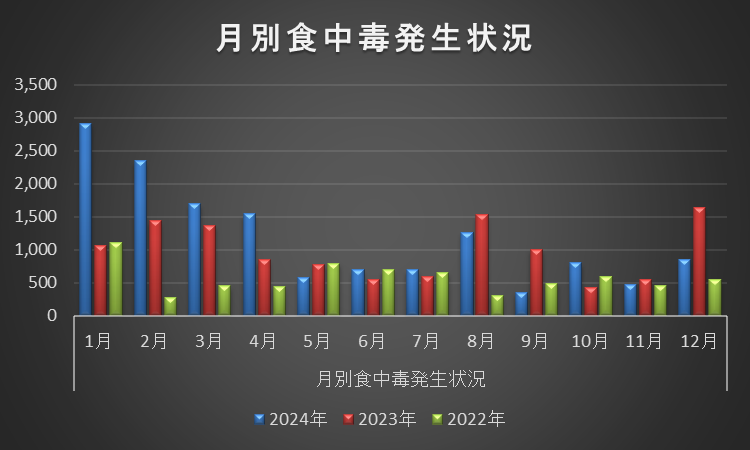
1.食中毒とは
食中毒は、有害な微生物(細菌、ウイルス、寄生虫など)や化学物質を含む食品を摂取することで起こる健康被害です。主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱などです。
2024年度 病因物質別食中毒発生件数グラフ
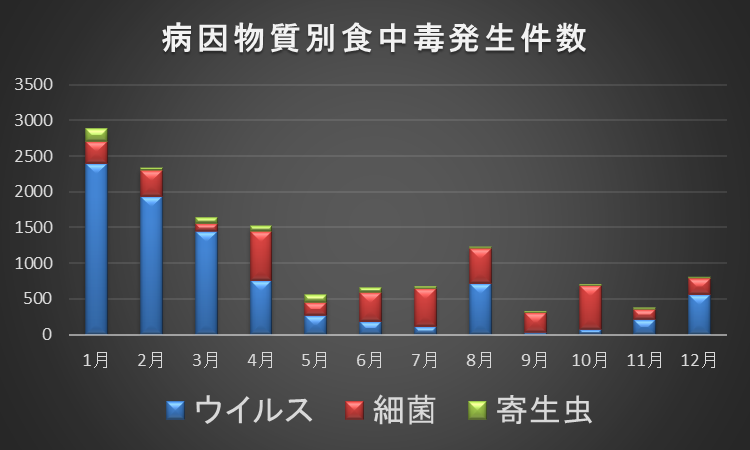
このグラフにおいて、春はウイルスによる食中毒が多く、夏・秋は細菌による食中毒が多くなり、また冬にウイルスによる食中毒が増えることがわかります。
夏に関してはこちら⇒医療コラム 夏に多い注意すべき食中毒とは!?ランキング形式で発表はこちら!
2.秋に多い主な食中毒の原因菌とは?
秋は気温が下がり過ごしやすくなる一方、食中毒原因では細菌によるものが多い時期です。行楽弁当や作り置き料理の常温放置、加熱不足のバーベキューなどで細菌が増殖しやすくなります。ウイルスや寄生虫も注意は必要ですが、秋特有の食習慣が細菌性食中毒の主な原因になります。
2-1.秋に多い細菌種別食中毒の件数推移とランキング
| 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ウエルシュ菌 | 4 | 326 | 78 | 408 |
| カンピロバクター | 168 | 127 | 53 | 348 |
| サルモネラ属菌 | 76 | 119 | 71 | 206 |
| ブドウ球菌 | 9 | 38 | 0 | 47 |
| 腸管出血性大腸菌 | 11 | 5 | 16 | 33 |
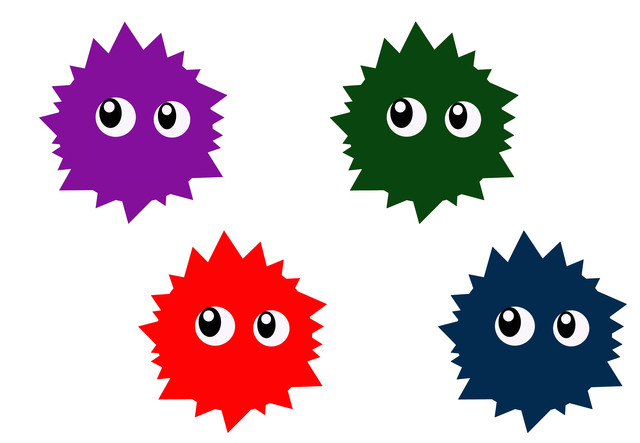
2-2.秋に多い食中毒原因菌ランキング別解説
秋は美味しい食材や行楽シーズンのイベントなど、食の楽しみが増える時期です。一方で、夏ほど気温は高くなくても油断は禁物。昼夜の寒暖差や常温放置による温度管理ミス、行楽での弁当持参、きのこ狩りや魚釣りなど自然食材の利用など、秋特有の食中毒リスクが潜んでいます。
ここでは、秋に特に注意したい食中毒の原因菌をランキング形式で紹介し、それぞれの特徴、感染源、症状、予防ポイントを詳しく解説します。秋の食卓を安全に楽しむために、ぜひ参考にしてください。
豊島区 おなかとおしりのクリニック 東京大塚も、地域の皆様の健康を応援します。
①ウエルシュ菌
特徴
学名:Clostridium perfringens
・芽胞を作るグラム陽性の棒状菌。酸素が少ない場所(嫌気性)で増殖します。
・芽胞は加熱しても生き残り、厳しい環境で長く潜伏。
病原性
・調理後に室温放置すると芽胞が発芽し増殖。
・腸内で「エンテロトキシン(CPE)」を作り、下痢や腹痛を起こします。
主な感染源
・大量調理後に常温で放置された料理。
カレー、シチュー、煮物、肉料理など。
「ゆっくり冷める」鍋が特に危険。
潜伏期間
・6〜18時間(多くは10〜12時間)。
・サルモネラやカンピロバクターより短めです。
症状
・腹痛。
・水様性の下痢。
・嘔吐は少なく、発熱もほとんどありません。
・1〜2日で自然に良くなることが多いです。
②カンピロバクター
特徴
・らせん状のグラム陰性菌。
・主な種は Campylobacter jejuni、C. coli。
・37〜42℃(鳥の腸の温度)でよく増殖します。
・酸素は少ない環境(微好気)を好みます。
病原性
・ほんの数百個程度でも感染。
・腸管にくっついて侵入し、炎症を起こします。
・粘膜を傷つけ、下痢を引き起こします。
主な感染源
・加熱不足の鶏肉、生食(鶏刺し、たたき)。
・汚染水や生乳。
・生肉を切った包丁やまな板で野菜を切るなどの交差汚染。
潜伏期間
・平均2〜5日(1〜7日程度)。
症状
・発熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛から始まることが多いです。
・その後、腹痛(鋭く、しつこい。右下腹部痛も)や下痢(時に血便)、嘔吐。
・大半は軽快するが、脱水には注意が必要。
診断
・便培養(特別な条件が必要です)。
・流行状況、食事歴、潜伏期間から推定することがあります。
③サルモネラ属菌
特徴
・グラム陰性の棒状菌で鞭毛による運動性あり。
・2000種類以上の血清型があり、感染源や流行の追跡に役立ちます。
病原性
・比較的多い菌量(10⁵〜10⁶個程度)で感染します。
・腸管のM細胞から侵入し、マクロファージ内で増殖します。
・腸の粘膜で炎症を起こして下痢を引き起こします。
主な感染源
・生卵、加熱不十分な卵料理。
・鶏肉、豚肉。
・未殺菌の乳製品。
・ペット(カメ、爬虫類など)。
・調理器具を介した交差汚染。
潜伏期間
・6〜72時間(通常12〜36時間)。
・カンピロバクターより短めです。
症状
・悪心、嘔吐。
・痙攣性でびまん性の腹痛。
・下痢(水様便、時に血便)。
・38〜39℃程度の発熱。
・大多数は軽症〜中等症で自然に回復。
④ ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌)
特徴
学名:Staphylococcus aureus
・グラム陽性の球菌。
・通性嫌気性で、塩分10%でも増殖可能。
・人の皮膚や粘膜に常在(手指、鼻腔など)。
病原性
・食品中で耐熱性の「エンテロトキシン」を産生します。
・加熱しても毒素は失活しにくい。
・汚染された食品を食べることで中毒を起こします。
主な感染源
・調理者の手指の傷、化膿巣。
・鼻腔からの保菌。
・汚染された調理器具。
・おにぎり、弁当、サンドイッチ、菓子パン、クリーム系食品。
潜伏期間
・1〜6時間(平均2〜3時間)。
・食中毒原因菌の中でも非常に短いです。
症状
・急激な発症。
・激しい吐き気、嘔吐。
・腹痛。
・軽度の下痢。
・発熱は軽度またはありません。
・多くは12〜24時間で自然軽快します。
3.食中毒予防のポイント
食中毒を防ぐには、細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則が大切です。以下に、家庭でできる具体的な対策を紹介します。(厚生労働省発行)
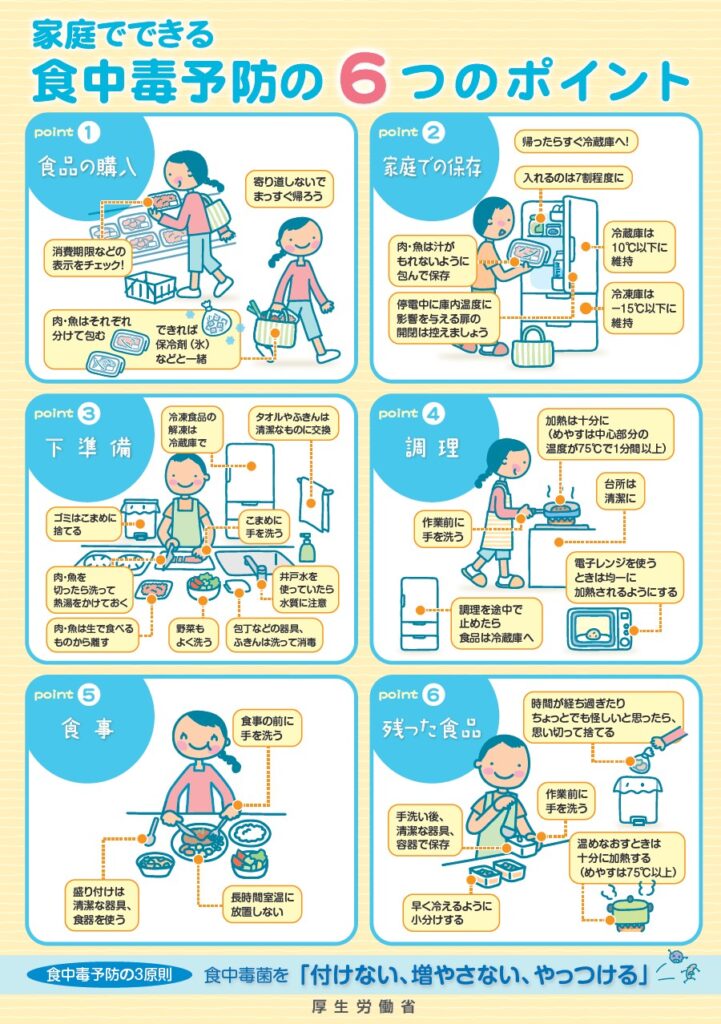
3-1️⃣ 食材を清潔に扱う
手洗いを徹底する
・調理前、食材を触る前後、トイレの後などは石けんでしっかり手を洗いましょう。
・指の間や爪の間も忘れずに。
・生肉・魚介類と他の食材を分ける
・生肉や魚介を切った後の包丁やまな板はすぐ洗い、できれば熱湯消毒。
・生の食材用と加熱後・野菜用で包丁やまな板を使い分けるのがおすすめ。
3-2️⃣ 十分な加熱をする
中心部までしっかり火を通す
・目安は「中心温度75℃で1分以上」。
・鶏肉やひき肉、ハンバーグ、卵料理などは特に注意。
・冷凍食品も表示通りに加熱しましょう。
3-3️⃣ 調理器具・台所を清潔に保つ
・調理器具は、使用後はすぐに洗浄・消毒
包丁、まな板、ふきん、スポンジなどは雑菌が繁殖しやすいので清潔を保つ。
ふきんやスポンジはこまめに熱湯消毒や漂白を。
・調理台も消毒を習慣に
特に生肉や魚を扱った後はアルコールスプレーや台所用漂白剤を薄めたものなどで拭く。
3-4️⃣ 低温保存を心がける
すぐ冷蔵庫へ
・調理後の料理は常温に放置せず、なるべく早く冷蔵保存。
・特に夏場は室温での放置が危険。
冷蔵庫の温度管理
・冷蔵室は10℃以下、冷凍室は−15℃以下を目安に。
・食品を詰め込みすぎないようにして冷気の流れを確保。
3-5️⃣ 体調管理と意識
体調が悪いときは調理を避ける
・嘔吐や下痢、発熱などがある場合は調理を他の人に任せましょう。
参考資料:厚生労働省「家庭での食中毒予防」
4.食中毒の対処法
・脱水予防が重要(経口補水液など)
・嘔吐・下痢止めの自己判断使用は避ける
(病原体の排出を阻害する場合がある)
・重症化のサイン(血便、高熱、意識障害、尿減少など)があれば早めに医療機関受診へ

5.まとめ
夏に特に注意すべき食中毒原因菌ランキング(発生件数ベース傾向)
1️⃣ ウェルシュ菌
2️⃣ カンピロバクター
3️⃣ サルモネラ属菌ブドウ球菌
4️⃣ ブドウ球菌
5️⃣ 腸管出血性大腸菌
詳細につきましては厚生労働省【食中毒】をご参照ください。

監修:おなかとおしりのクリニック 東京大塚
院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)
資格:日本消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
帝京大学医学部外科学講座非常勤講師
元帝京大学医学部外科学講座准教授
医学博士
院長プロフィール