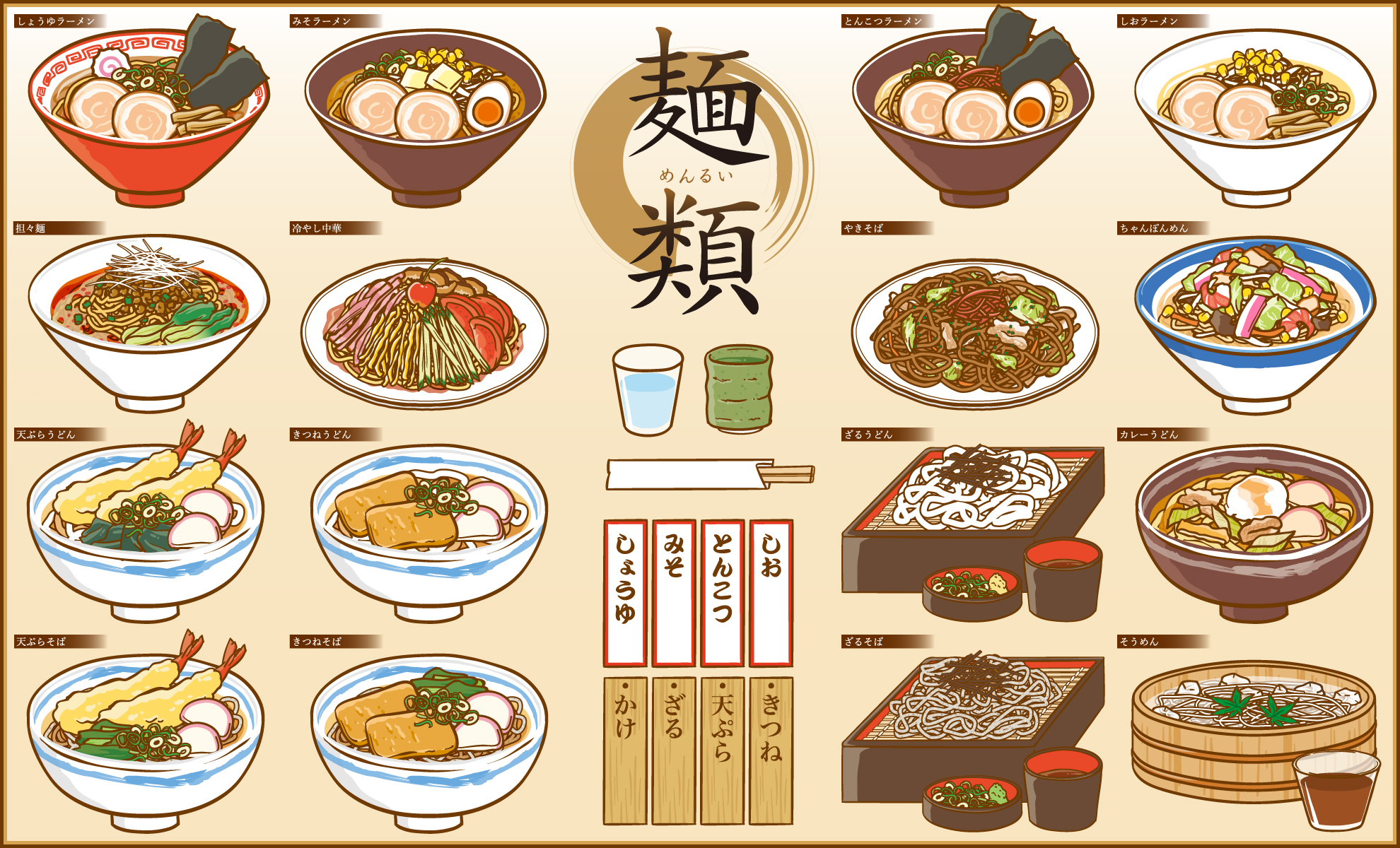2025年7月23日

「なんでもないところでつまずいた」「ちょっとした段差で転びそうになった」──そんな経験が増えていませんか?
実はそれ、“フレイル”と呼ばれる加齢による心身の衰えのサインかもしれません。フレイルは進行すると転倒・骨折・要介護にもつながりますが、早期に気づけば改善も可能です。
この記事では、つまずきやすさとフレイルの関係、チェック方法、予防と改善のポイントをわかりやすく解説します。
フレイルとは? ― 要介護リスクを高める“見えにくい衰え”
「なんとなく疲れやすくなった」「足腰が弱った気がする」──そんな小さな変化が、実はフレイルの始まりかもしれません。フレイルは早期に気づけば生活習慣の改善などで回復が期待できる、“健康と要介護の間”にある大切な状態です。
フレイルの定義と主な分類
フレイル(Frailty)とは、加齢にともなって筋力や身体機能、精神的活力、社会性などが少しずつ衰えていく状態です。 「健康」と「要介護」の間にある移行期とされ、適切な介入を行えば改善が期待できる可逆的な状態とされています。
代表的には、以下の3つの側面に分けて評価されます:
| フレイルの分類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 身体的フレイル | 筋力低下、歩行速度の低下、転倒、つまずきやすさ |
| 心理的・認知的フレイル | 抑うつ傾向、認知機能の低下、意欲の減退 |
| 社会的フレイル | 孤立、外出機会の減少、社会参加の喪失 |
※分類は一例であり、より詳細に4~5分類する見解もあります。
つまずきやすさは、フレイルの重要なサインのひとつ
「足が上がりにくい」「つま先がひっかかる」といった小さな変化は、身体機能の衰えの兆候であり、身体的フレイルのサインである可能性があります。
下肢筋力やバランス機能の低下が背景にある
加齢に伴い、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)や足関節周囲の筋肉が衰えると、歩行時に足が十分に上がらなくなり、段差や絨毯などのわずかな障害物につまずくことが増えます。
また、姿勢を維持する体幹筋やバランスを取る前庭機能の低下も、ふらつきや転倒リスクを高めます。
つまずきやすさは他の病気(神経障害・視覚異常・筋骨格疾患)でも起こるため、単独で診断にはなりませんが、フレイルの重要な兆候のひとつとして注意が必要です。
自宅でできる!フレイル簡易チェック(J-CHS基準準拠)
「自分はまだ大丈夫」と思っている方も、気づかないうちにフレイルが始まっている可能性があります。以下のチェックでセルフ評価してみましょう。
✅ このチェックは、日本人高齢者向けに作られた「J-CHS(Japanese Cardiovascular Health Study)」のフレイル評価基準に準拠しています。
| チェック項目 | 内容の説明 |
|---|---|
| ① 体重減少 | 半年で2kg以上の体重減(意図しない) |
| ② 疲れやすさ | 「何をするのも面倒」「活力が湧かない」と感じる |
| ③ 身体活動の低下 | 散歩や買い物など、軽い活動が減っている |
| ④ 歩行速度の低下 | 歩く速度が以前より遅くなった |
| ⑤ 筋力の低下 | ペットボトルのふたが開けづらい、握力が弱くなった |
→ 3項目以上当てはまる方は、医療機関での評価をおすすめします。

参考文献:Satake S, et al. Prevalence of frailty among community-dwellers and outpatients in Japan as defined by the Japanese version of the Cardiovascular Health Study criteria. Geriatr Gerontol Int. 2017 Dec;17(12):2629-2634. doi: 10.1111/ggi.13129.
フレイルとサルコペニアの違い ― 混同されやすいが、意味は異なる
「サルコペニアって聞いたことがあるけど、フレイルとどう違うの?」という疑問はよくあるものです。ここで明確に整理しておきましょう。
似ているようで違う2つの概念
| 比較項目 | フレイル | サルコペニア |
|---|---|---|
| 概念 | 多面的な加齢による衰え(体・心・社会) | 筋肉量・筋力・身体機能の低下に特化 |
| 主な影響 | 転倒・骨折・認知機能低下・要介護 | 歩行障害・転倒 |
| 診断方法 | J-CHSチェック、体重変化、歩行速度など | BIA/DXAでの筋肉量測定、握力、歩行速度 |
| 関連学会 | 日本老年医学会、日本フレイル学会 | 日本サルコペニア・フレイル学会、日本骨粗鬆症学会 |
🧠【補足】
サルコペニアは「身体的フレイル」の一部として捉えられますが、単独の診断対象にもなっており、近年はがん、糖尿病、慢性心不全などとの関係も注目されています。
日本人高齢サルコペニア患者の腸内フローラ(腸内細菌叢)の特徴
近年、サルコペニア(筋肉量と筋力が加齢とともに低下する状態)と腸内フローラ(腸内細菌叢)の関係に注目が集まっています。日本人高齢者を対象とした研究では、筋力低下と特定の腸内細菌の減少との関連が報告されており、とくに男性で顕著な特徴が観察されています。

腸内で酪酸産生菌が減少 ― 筋力低下と関連か
日本人の男性サルコペニア患者の腸内では、酪酸(らくさん)を産生する腸内細菌が健常者と比べて減少していることがわかりました。
🔍【用語解説】
酪酸(Butyrate)は、腸内細菌が食物繊維などを発酵して産生する短鎖脂肪酸の一種で、腸管のバリア機能維持や免疫調節、さらには筋タンパク質の合成促進や炎症の抑制にも関与する重要な代謝物です。
健康な高齢者の腸内では酪酸産生菌の占有率が高いことが報告されており、これが筋力維持に役立っている可能性が示唆されています。
フラボノイドを代謝するEubacterium ramulusとの関係
本研究では、酪酸産生菌のひとつとして知られる**Eubacterium属の中の「Eubacterium ramulus(E. ramulus)」**にも注目されました。
この細菌は、野菜や果物に含まれる**フラボノイド(ポリフェノールの一種)**を腸内で代謝する働きがあり、代謝産物が抗炎症作用や筋萎縮抑制効果を持つ可能性があるとされています。
✅ フラボノイド:野菜や果物に多く含まれる抗酸化物質の一種。筋肉の老化や萎縮を抑える働きが注目されています。
女性では同様の腸内細菌の変化はみられなかった
本研究で特に注目すべき点は、酪酸産生菌の減少やE. ramulusの低下といった腸内フローラの変化が、男性に特異的に見られたことです。女性のサルコペニア患者では、こうした菌の顕著な変化は観察されませんでした。これは、筋力と腸内細菌の関係が性別で異なる可能性を示唆しており、将来的な介入や栄養指導においても男女別のアプローチが必要となる可能性があります。
参考文献:Daisuke Asaoka, et al. Sex-Specific Associations of Gut Microbiota Composition with Sarcopenia Defined by the Asian Working Group for Sarcopenia 2019 Consensus in Older Outpatients: Prospective Cross-Sectional Study in Japan. Nutrients. 2025 May 21;17(10):1746. doi: 10.3390/nu17101746.
フレイルは予防・改善できる!生活習慣3本柱
フレイルは進行性の状態ではありますが、初期の段階であれば“回復可能”な点が特徴です。ポイントは、栄養・運動・社会参加の3本柱。
フレイル予防・改善のための生活習慣
| 項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 栄養 | タンパク質・ビタミンD・亜鉛などを意識した食事や補助食品の活用 |
| 運動 | スクワット、かかと上げ、ウォーキング、ラジオ体操など継続できる軽運動 |
| 社会参加 | 友人との交流、趣味活動、地域ボランティアなど孤立を防ぐ行動 |
まとめ:早期に気づけば、対策はできる
・「つまずき」は身体機能低下の重要なサインのひとつ
・フレイルは早期に気づけば改善可能なことが多い状態
・栄養・運動・社会参加の3本柱を意識し、継続的な予防を
・気になる兆候があれば、医療機関での評価・相談をおすすめします
腸内フローラ検査のすすめ

腸内環境(腸内フローラ)は目に見えませんが、全身の健康や加齢による筋力の低下とも深く関わっていることが、近年の研究で明らかになってきました。
特にサルコペニアやフレイルの予防・改善において、腸内フローラの状態を把握することは、食事や生活習慣を見直す大きなヒントになります。
当院では、腸内環境のバランスや酪酸産生菌の状態などを可視化できる「腸内フローラ検査」を行っております。東京でご自身の腸内環境が気になる方、将来の健康に備えたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

監修:東京都豊島区おなかとおしりのクリニック 東京大塚
院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)
資格:日本消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本大腸肛門病学会指導医・専門医・評議員
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
帝京大学医学部外科学講座非常勤講師
元帝京大学医学部外科学講座准教授
医学博士