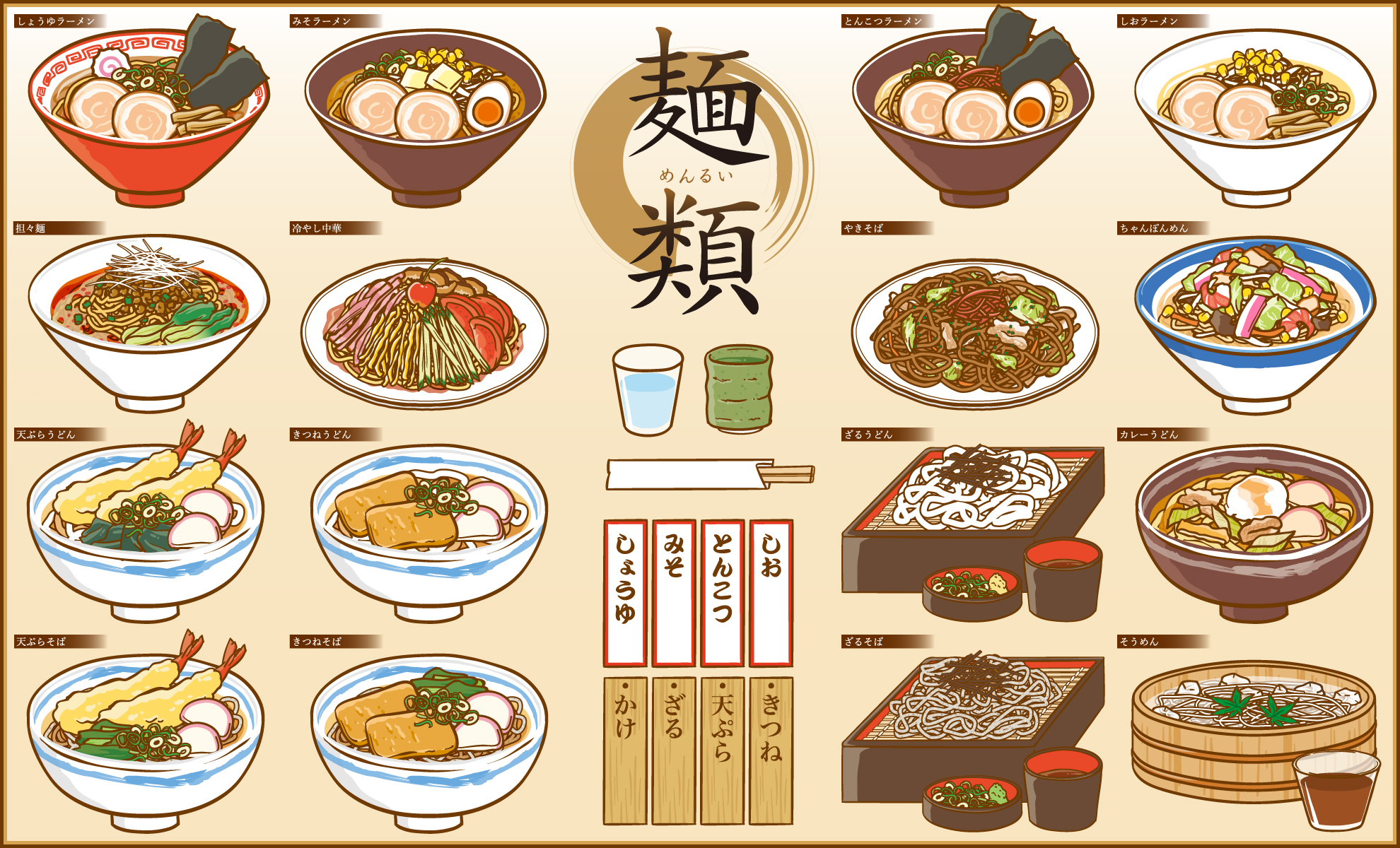2026年1月29日

ピロリ菌は胃の中に住む細菌で、胃がんや胃潰瘍の主な原因です。しかし、検査で早期発見し除菌治療を行えば、胃がんのリスクを大幅に減らすことができます。感染していても無症状のことが多いため、50歳以上の方は一度検査を受けることが推奨されます。この記事では、ピロリ菌の感染原因から検査・除菌治療まで分かりやすく解説します。
ヘリコバクター・ピロリ菌とは?
ヘリコバクター・ピロリ菌(H. pylori)は、人の胃の中に住むらせん状の細菌です。

ピロリ菌の正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ」といい、らせん状の形をした細菌です。胃の中は強い酸性(pH1〜2)のため通常の細菌は生息できませんが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を作り出し、胃の中の尿素を分解してアンモニアを生成します。このアンモニアで胃酸を中和し、自分の周囲をアルカリ性に保つことで、強い胃酸の中でも生存できるのです。
ピロリ菌は1983年にオーストラリアの研究者によって発見され、2005年にはノーベル医学生理学賞を受賞しました。日本のピロリ菌感染者数は約3,500万人といわれ、特に60歳以上の方で高い感染率となっています。
また、胃粘液層の下に潜り込むことで免疫の攻撃を避け、長期間にわたって胃の粘膜に炎症を起こします。
長期感染により「慢性胃炎(萎縮性胃炎)」が進行し、胃がんのリスクが上がることがわかっています。
ピロリ菌の感染原因と経路
ピロリ菌の感染は主に5歳までの幼少期に起こります。幼少期は胃酸の分泌が少なく、免疫機能も未発達なため、ピロリ菌が胃に定着しやすい環境にあるためです。成人になってから新たに感染することはほとんどありません。
主な感染経路
・親から子へのピロリ菌感染
・食器の共有
・井戸水や生水の飲用
・衛生環境が整っていない時代の経口感染
日本では上下水道の普及により、若い世代の感染率は大きく低下しています。10〜20代では10%前後ですが、50代以上では40%程度、60歳以上では60%以上と、年齢が高いほど感染率が高くなっています。これは、上下水道が整備される前の幼少期を過ごした世代が、感染の機会が多かったためと考えられています。
| 年齢層 | 感染率 |
|---|---|
| 10〜20代 | 約10% |
| 50代 | 約40% |
| 60歳以上 | 60%以上 |
参考文献
日本ヘリコバクター学会. ガイドライン 2022改訂版.
Kivi M, et al. Gastroenterology. 2005;128(7):1755–1762.
Goodman KJ, Correa P. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2000;5(Suppl 1):S2–S6.
ピロリ菌が引き起こす症状と病気
ピロリ菌に感染しても、多くの方は自覚症状がありません。しかし、感染したほぼ100%の人に胃炎が起こり、放置すると様々な病気を引き起こすリスクが高まります。
感染時に現れる可能性のある症状
・胃もたれ、吐き気
・みぞおちの痛み
・胸やけ
・食欲不振
・ゲップが多い
ただし、これらの症状が出ない場合も多いため、症状の有無に関わらず検査を受けることが重要です。
ピロリ菌が原因となる主な病気
| 病気 | 特徴 | ピロリ菌との関連 |
|---|---|---|
| 慢性胃炎 | 胃粘膜の慢性的な炎症 | 感染者のほぼ100%が発症 |
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 胃や十二指腸の粘膜に深い傷 | 患者の80〜90%が感染 |
| 萎縮性胃炎 | 胃粘膜が薄くなり機能低下 | 長期感染で進行 |
| 胃がん | 胃粘膜の悪性腫瘍 | 感染者の約10%が発症 |
| 胃MALTリンパ腫 | 胃の悪性リンパ腫 | 患者の90%が感染 |
特に注意すべきは、胃がんの原因の約99%がピロリ菌感染によるものだという点です。ピロリ菌による慢性胃炎が萎縮性胃炎へと進行し、さらに高塩分食や喫煙などの要因が重なることで、胃がんのリスクが高まります。
ピロリ菌感染はどんな検査法でわかるの?
ピロリ菌の有無を調べる検査は、内視鏡検査を使う方法と使わない方法の2つに大きく分けられます。

内視鏡(胃カメラ)を使わないピロリ菌の検査方法
| 検査名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 尿素呼気試験 | 検査薬を飲み、呼気を採取 | 精度が最も高く主流の検査 |
| 抗体測定 | 血液や尿で抗体を測定 | 簡便だが除菌判定には不向き |
| 便中抗原検査 | 便中のピロリ菌抗原を検出 | 非侵襲的で精度も高い |
内視鏡を使うピロリ菌の検査方法
| 検査名 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 迅速ウレアーゼ試験 | 胃粘膜を採取し試薬で反応 | 当日に結果が分かる |
| 組織鏡検査 | 胃粘膜を顕微鏡で観察 | 菌を直接確認できる |
| 培養法 | 胃粘膜から菌を培養 | 除菌後の判定に有効 |
最も一般的なのは、精度が高く体への負担も少ない「尿素呼気試験」です。ただし、ピロリ菌検査は偽陰性(感染しているのに陰性と出る)の可能性もあるため、疑わしい場合は複数の検査方法を組み合わせることが推奨されます。

ピロリ菌除菌はしたほうがいいの?その除菌治療の方法は?
ピロリ菌が見つかった場合、除菌治療を行うことで胃がんや潰瘍のリスクを大きく減らすことができます。

ピロリ菌除菌をおすすめする理由
胃がんのリスクを減らす
ピロリ菌は慢性的な胃炎を引き起こし、長年放置すると胃潰瘍や胃がんの原因になることが分かっています。
除菌治療をすることで、将来の胃がんリスクを有意に減らせることが科学的に証明されています。
世界保健機関(WHO)の**国際がん研究機関(IARC)は、ピロリ菌を「グループ1の発がん因子」**に分類しています。
これは「人で発がん性があることが十分に証明された因子」という意味であり、ピロリ菌に感染している人は感染していない人よりも胃がんになるリスクが有意に高いことが示されています。
ただし、ピロリ菌感染者全員が必ず胃がんになるわけではありません。
そのため、ピロリ菌感染が確認された場合には、胃がん予防のために保険診療でのピロリ菌除菌治療が推奨されています。
日本では特に中高年層で感染率が高く、胃がん対策として重要視されています。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防
ピロリ菌は潰瘍を繰り返す大きな原因です。除菌することで再発を防げます。
症状の改善
慢性胃炎による胃もたれや不快感などが軽減することがあります。
治療方法(除菌方法)
除菌療法は、1種類の胃酸分泌抑制薬と2種類の抗菌薬を組み合わせた「3剤併用療法」が基本です。これらの薬を1日2回、7日間続けて服用します。
✅ 注意点
除菌治療を行うことで胃がんリスクを下げられることが証明されていますが、完全に防げるわけではありません。
除菌後も定期的な胃内視鏡検査が重要です。
除菌治療の流れ
1.一次除菌(7日間服薬)
2.8週間後に除菌判定検査
3.除菌失敗の場合は二次除菌(薬を変更して7日間)
4.再度、除菌判定検査
- 一次除菌:約80%
- 二次除菌:ほぼ100%
一次除菌で失敗しても、二次除菌を行えばほとんどの場合で除菌に成功します。
ピロリ菌が除菌できたか確認した方がいいの?
ピロリ菌の除菌後は再感染や治療失敗を見逃さないために、判定検査を受けることが強く推奨されています。
ピロリ菌除菌判定検査方法
・尿素呼気試験
・便中抗原検査
検査時期
ピロリ菌除菌終了後、8週以上経過してから
除菌治療中の注意点と副作用
よくある副作用として、軟便・下痢、味覚異常、発疹などがあります。軽い症状の場合は自己判断で中止せず、7日間しっかり服用することが大切です。ただし、激しい下痢や発熱を伴う場合は、すぐに医師に相談してください。
また、二次除菌中はアルコールの摂取を避ける必要があります。薬との相互作用で、顔面紅潮や動悸などの症状が出ることがあるためです。
除菌に成功すると、新たな胃がんの発生リスクが大幅に低下することが研究で確認されています。
参考文献
IARCのリリースはこちら⇒IARC calls on countries with high stomach cancer burden to act to prevent the disease
日本ヘリコバクター学会. H. pylori感染の診断と治療のガイドライン2024年版.
おなかとおしりのクリニック 東京大塚の胃内視鏡の特徴
当院では、患者様の不安を和らげ、安心して受けていただける胃カメラ検査を提供しています。豊島区エリアのかかりつけ医として、苦痛を抑えた検査ときめ細やかなサポートを大切にし、一人ひとりに寄り添った医療を心がけています。
苦痛を抑えた胃内視鏡検査で、豊島区で安心して受けられる医療を
おなかとおしりのクリニック 東京大塚では、「苦しくない」「怖くない」胃カメラ検査をめざし、鎮静剤を用いたやさしい内視鏡検査を行っています。鎮静剤を使用することで、ウトウトと眠ったような状態で検査が可能になり、嘔吐反射や不快感を最小限に抑えられるのが特長です。消化器内視鏡専門医が担当し、患者様の不安を軽減しながら、豊島区エリアの皆さまに安心して受けられる検査環境を整えています。
胃がん検診としても重要な早期発見・精密検査
当院の胃カメラ検査は、慢性胃炎、ピロリ菌感染の評価、胃潰瘍、胃がんの早期発見に役立ちます。特に胃がん検診として胃カメラ検査(内視鏡検査)を受けることは、バリウム検査よりも小さな病変を見逃しにくいのが大きな利点です。必要に応じて組織検査(生検)をその場で実施し、がんの有無やピロリ菌感染の診断を正確に行います。豊島区で精密な胃がん検診を希望される方に、信頼できる検査体制を提供しています。
土曜・早朝対応や女性医師担当日も
おなかとおしりのクリニック 東京大塚では、忙しい方にも受診しやすいよう土曜や早朝の胃カメラ検査を実施。女性医師による対応日(火曜日)も設けており、女性の患者様も安心してご相談いただけます。院内での下剤内服対応など、患者様の負担軽減を重視した柔軟な運営で、地域のかかりつけ医として「豊島区で胃カメラ検査を受けるならここ」と思っていただけるクリニックを目指しています。
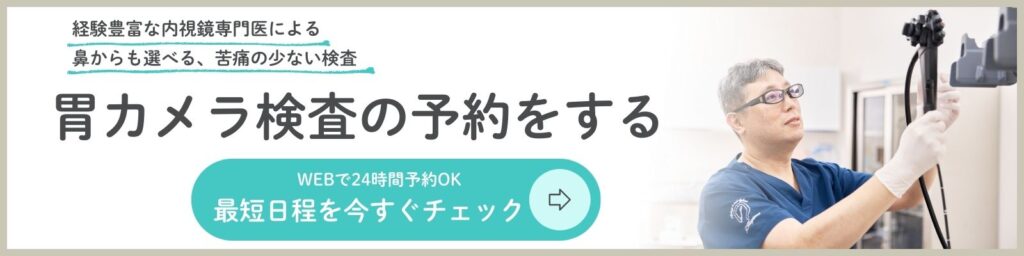
ピロリ菌に関するよくある質問
まとめ
ピロリ菌感染は胃がんのリスクを高める重要な要因ですが、感染しても全員が胃がんになるわけではありません。
ピロリ菌除菌治療を受けることでリスクを下げられることが証明されていますが、ゼロにはできないため、ピロリ菌除菌後も定期的な胃内視鏡検査が重要です。

監修:おなかとおしりのクリニック 東京大塚
院長 端山 軍(MD, PhD Tamuro Hayama)
資格:日本消化器病専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会専門医・指導医
日本大腸肛門病学会専門医・指導医・評議員
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
帝京大学医学部外科学講座非常勤講師
元帝京大学医学部外科学講座准教授
医学博士
院長プロフィールはこちら